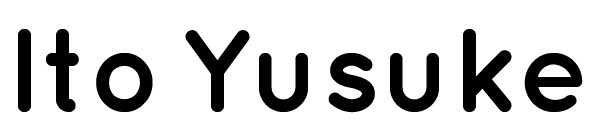スライドやプレゼン資料を作るとき、配色選びは見た目の印象だけでなく、情報の伝わりやすさにも直結します。色は単なる装飾ではなく、メッセージや感情を伝える重要な要素です。
同じレイアウトでも、色を変えるだけで「信頼感がある」「活発な印象」「落ち着いた雰囲気」など、受け手の印象は大きく変わります。
この記事では、主要な6種類の色のイメージ(モノクロ・青・緑・赤・黄・カラフル)と、それぞれの効果的な使い方、避けたいNG例を解説します。
モノクロ|シンプル・洗練・プロ感
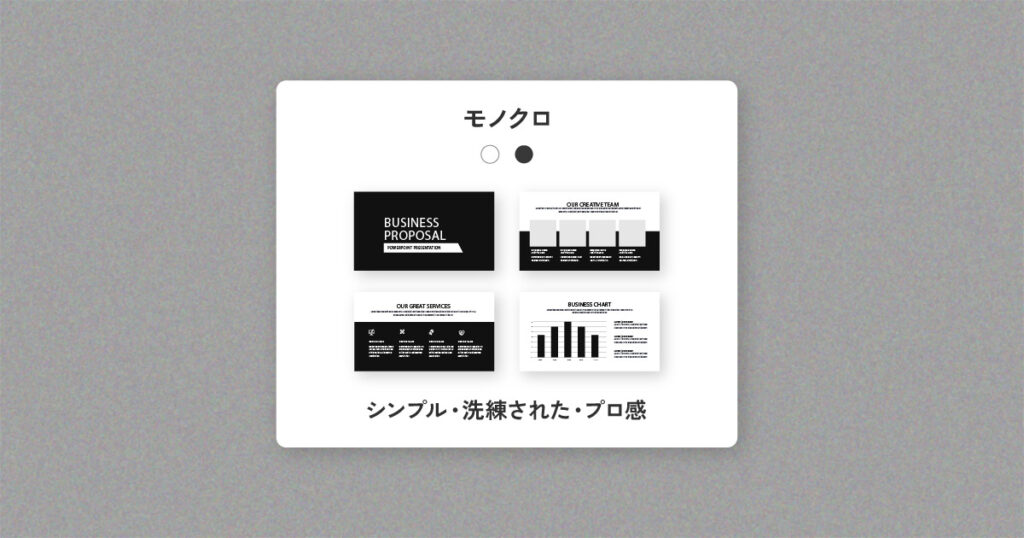
余計な情報をそぎ落とし、要点だけに集中させたい時はモノクロが最強です。経営層へのレポート、研究発表、ブランドの世界観をストイックに見せたい資料と好相性。
使い方のコツ
- 写真は白黒化すると情報密度が整い、図表との一体感が出ます
- フォントは太さのコントラストで抑揚をつける
NG: すべて同じ黒でベタ塗り。階調がないと重く読みにくくなります
青|信頼・冷静・誠実

コーポレートサイトやSaaS、金融、医療など安心して任せられる印象を出したいときに。数値やグラフとも親和性が高く、情報設計が整って見えます。
使い方のコツ
- 濃淡のグラデーションで面を分けると清潔感が増す
- NG: 彩度の低い青だけで組むと沈んだ雰囲気に。重要箇所には少し鮮やかさを
緑|ナチュラル・安心・調和

サステナビリティ、健康、福利厚生、組織文化など人や環境に寄り添うテーマに。長文の資料でも目の疲れを感じにくいのも利点です。
使い方のコツ
- 緑=「良い」を表す記号的意味を活かし、チェックや達成状況の表示に
- ベースはやわらかい黄緑、強調は深いグリーンにすると上品
注意: 赤緑色覚の配慮が必須。重要な区別は色だけに頼らず形や線の種類も併用しましょう
赤|情熱・エネルギッシュ・インパクト

視線を一瞬で奪う警告色。CTAボタン、キャンペーン、注意喚起など「ここを見て」を作りたい時に効果的です。
使い方のコツ
- 面で大量に使うより、ピンポイントに使うほど効く
- グレーや黒の落ち着いた土台に、赤5%で締めると洗練される
NG: 文章背景を真っ赤にすると、可読性が下がり疲れやすい
黄|明るさ・ひらめき・楽しさ

アイデア、学び、エンタメ系にぴったりな陽の色。注目を集めやすい反面、扱いを誤ると軽く見えがちです。
使い方のコツ
- 文字色は濃いめの黒と組み合わせてコントラストを確保
- まぶしすぎるレモンイエローは小面積に留め、面には少し落ち着いたマスタード系を
NG: 白背景×淡い黄色のテキスト。←読みづらくなるので注意
カラフル|元気・個性・多様性

採用・コミュニティ・教育など、多様な人や価値観を表す時に。楽しい空気をつくれます。
使い方のコツ
- 何色も使うほど役割のルールが重要。カテゴリごとに色を固定し、凡例を必ず表示
- すべて高彩度にしすぎない。
NG: 意味のない虹色。情報が散らばり読者が迷子になります
配色比率と役割

図解やスライドでは、色ごとの役割分担を明確にすることで、見やすく伝わりやすいデザインになります。基本的には「Main(メインカラー)」「Sub(サブカラー)」「Accent(アクセントカラー)」の3つに分類されます。
- Main(メインカラー)
デザイン全体の主役となる色。テーマやブランドを象徴し、目立たせたい要素に使います。割合は中くらいに抑え、画面に統一感を出す役割があります。 - Sub(サブカラー)
メインを引き立てる脇役。本文や背景、図表の台など、落ち着いたトーンで構成します。面積はやや広めに取り、メインを邪魔しない色が理想です。 - Accent(アクセントカラー)
重要な情報や注目してほしい部分に使う差し色。面積は小さく、メインカラーを補完する色を選びます。使いすぎると効果が薄れるため注意が必要です。
このように「主役・脇役・差し色」の関係を意識するだけで、情報の優先順位が視覚的に伝わり、スライド全体が整理されて見えます。
まとめ
- モノクロは情報集中、青は信頼、緑は安心、赤はインパクト、黄は楽しさ、カラフルは多様性
- 配色はメイン・サブ・アクセントの3役で役割分担
- メイン:テーマや主役部分
- サブ:背景や補助的要素
- アクセント:重要な情報や強調点 - 目的と読者から逆算し、情報に優先順位のルールをつける
色は見た目を整えるだけでなく、情報の「伝わり方」をコントロールする力があります。次のスライドや図解づくりに、ぜひこの3役配色を取り入れてみてください。