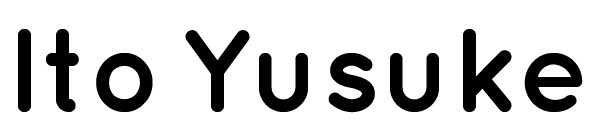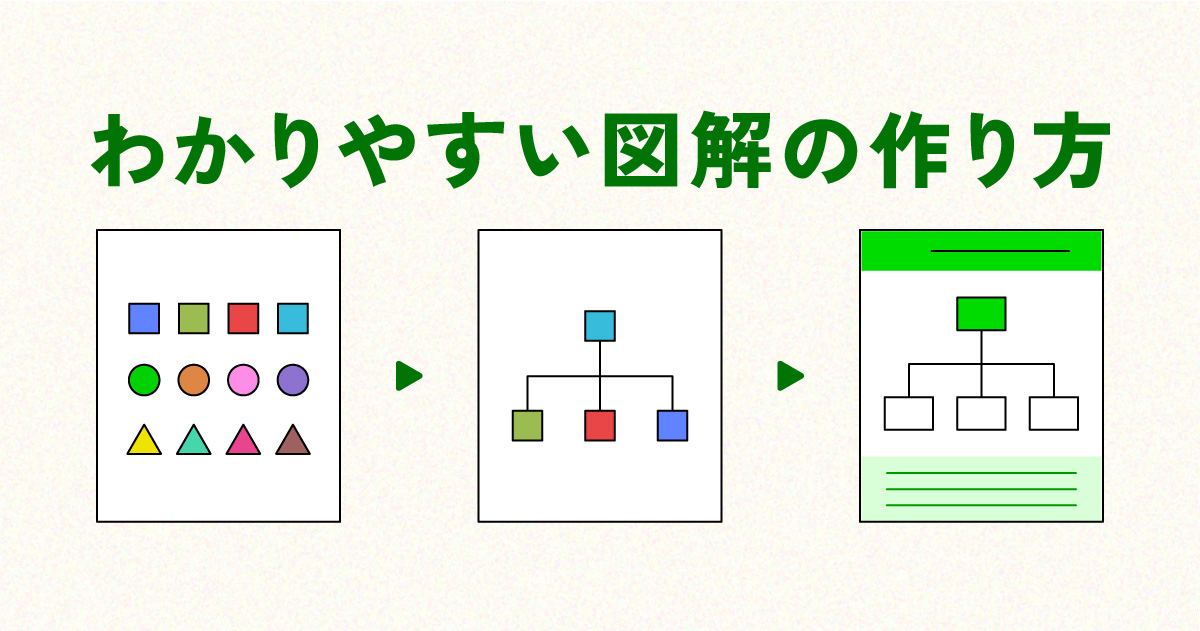この記事では、「わかりやすい図解ってどう作ればいいの?」という方に向けて、図解の基本ステップを3つに分けて解説します。
図解に必要なのは「3つの力」
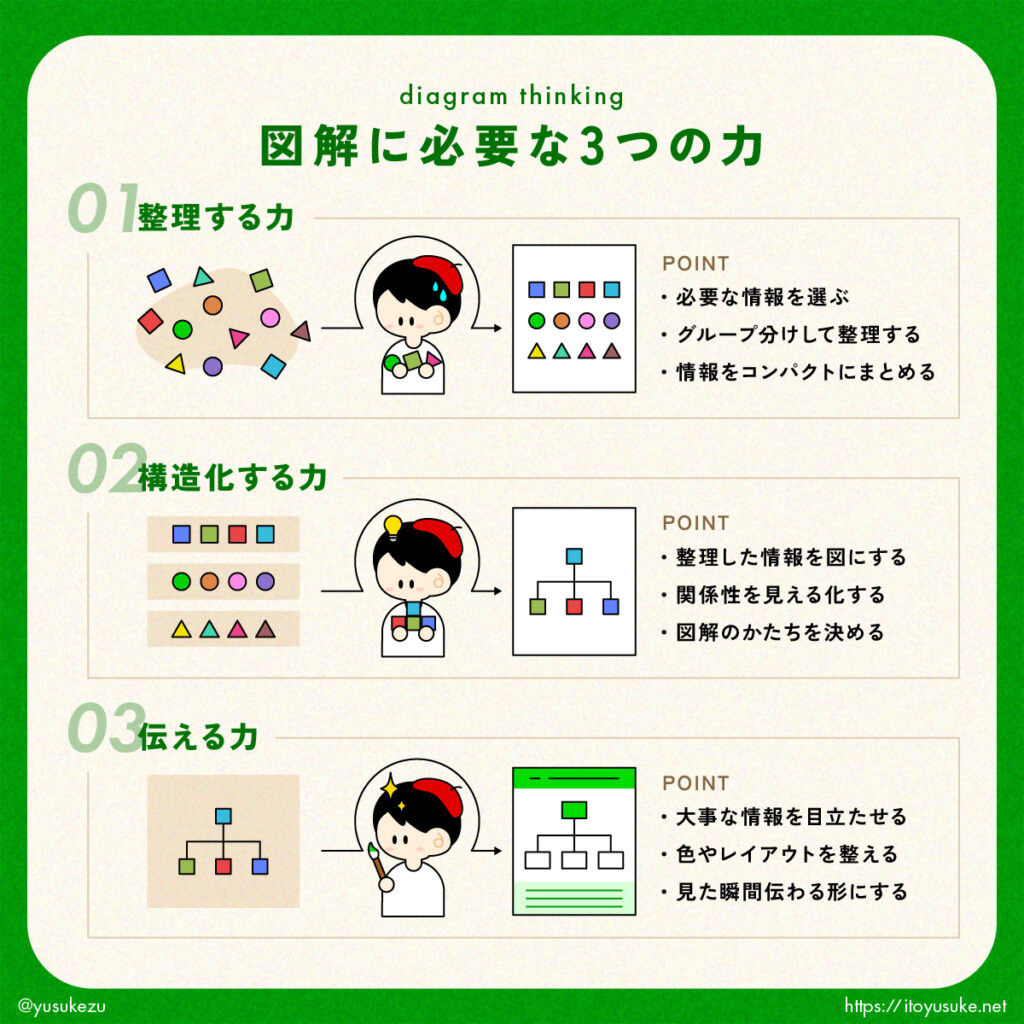
図解を作るときに大切なのは、以下の3つの視点です。
① 情報を「整理する力」

まずは、伝えたい内容を整理するところからスタート。どんなに綺麗でおしゃれなデザインでも、情報がごちゃごちゃしていたら、そもそも伝わりません。
- 不要な情報を削る
- グループに分ける
- コンパクトにまとめる
この3点を意識してみましょう。
② 情報を「構造化する力」

整理された情報を、図として組み立てていくステップです。並べる順番や関係性の見せ方を決めることで、「一目で伝わる」図解になります。
- どの情報同士が関係している?
- どの順番で見せたい?
- 当てはめる図解の型は?
など、自分なりのロジックを持つことがポイントです。
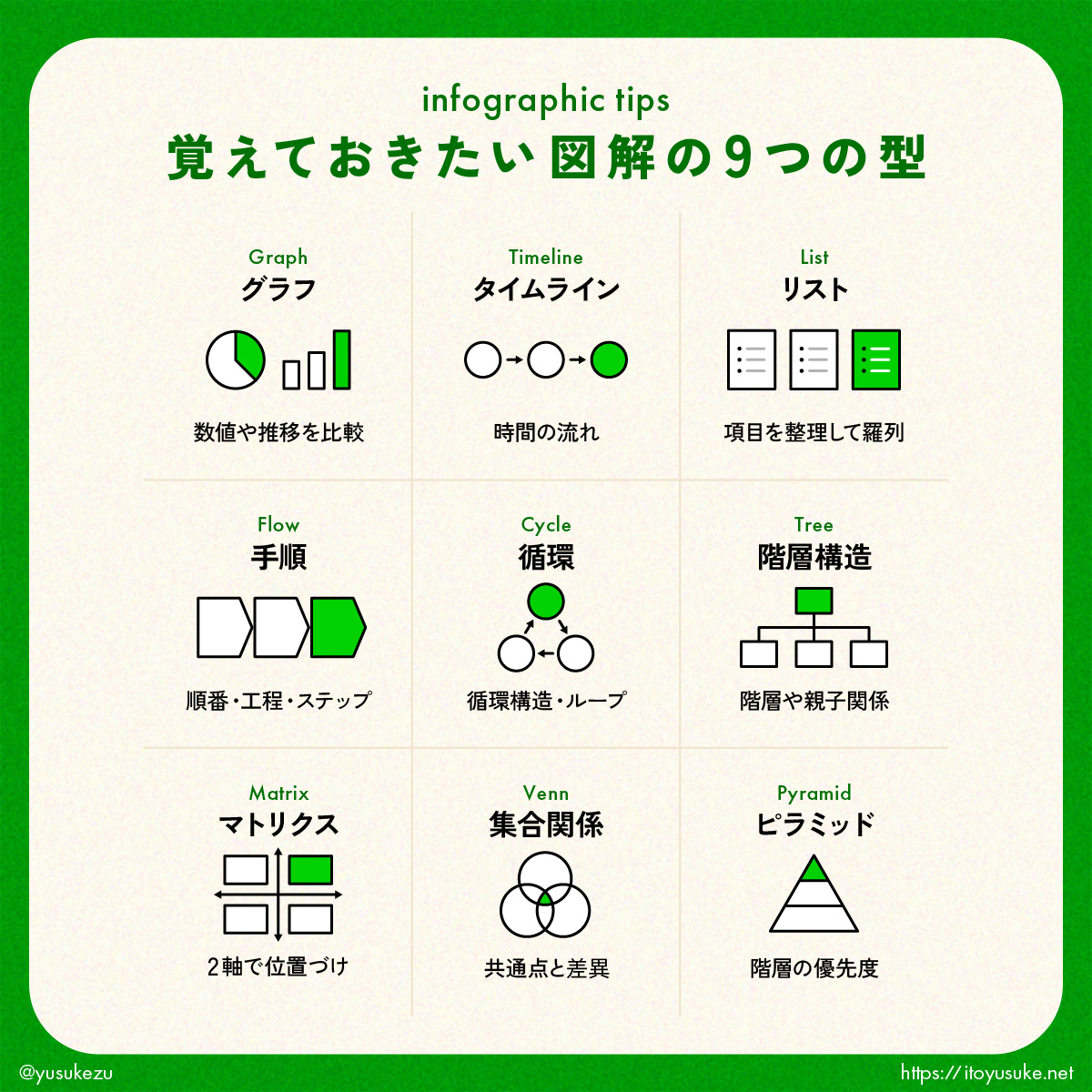
③ 情報を「伝える力」
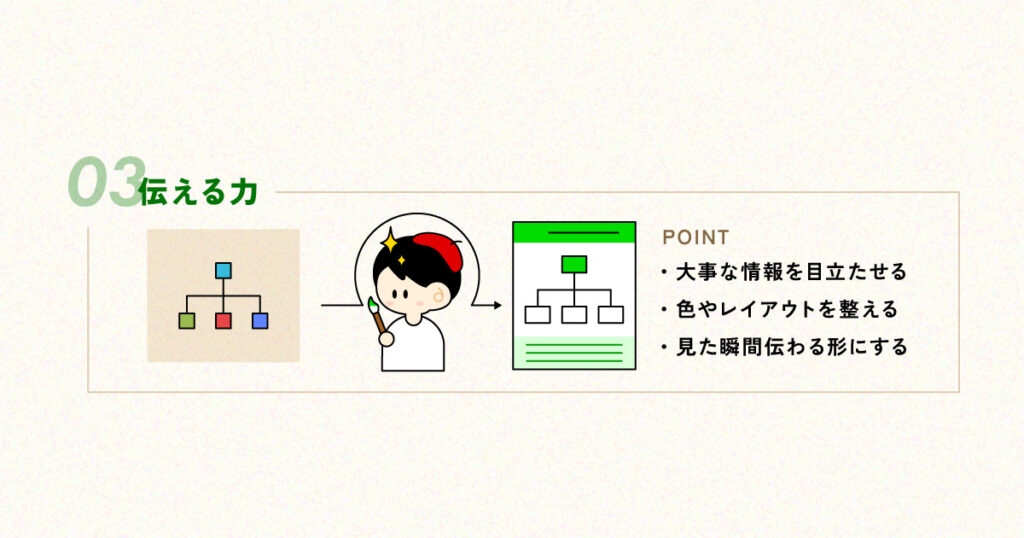
最後は「見た目」の工夫。同じ内容でも、伝え方ひとつで印象は大きく変わります。
- 重要な情報を目立たせる
- 配色・文字サイズで視線を誘導する
- 一瞬で伝わるレイアウトに整える
「伝えるデザイン」に仕上げることで、図解の効果はぐっと上がります。
実際の図解化プロセス|例を見ながら解説
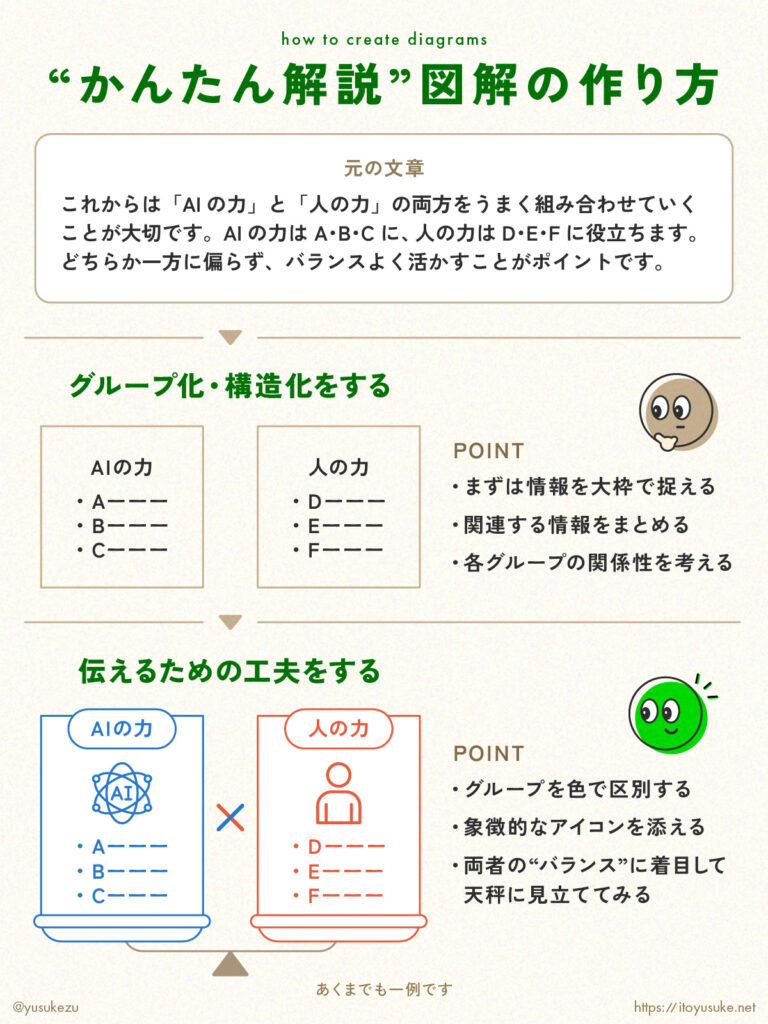
ここからは、実際の例をもとに図解の作り方を解説します。
元の文章
これからは「AIの力」と「人の力」の両方をうまく組み合わせていくことが大切です。AIの力はA・B・Cに、人の力はD・E・Fに役立ちます。どちらか一方に偏らず、バランスよく活かすことがポイントです。
このままだとちょっと分かりにくいですね。
ステップ①:グループ化・構造化する
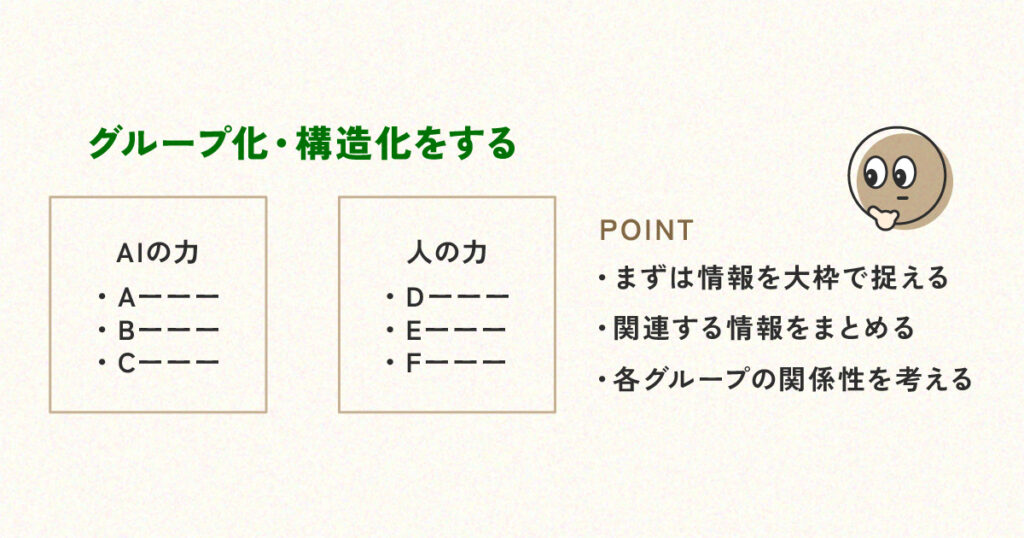
まず、「AIの力」「人の力」をそれぞれのグループとして分けます。その上で、それぞれの特徴(A〜F)を箇条書きで整理。
この時点で、「2つの視点があるんだな」という構造が見えてきます。
ステップ②:伝えるための工夫をする
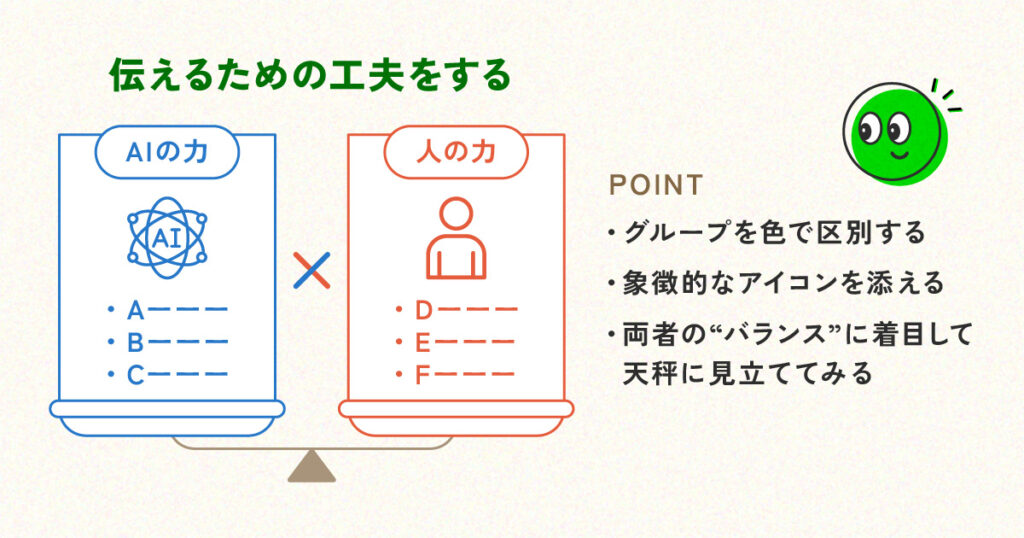
次に、
- アイコンで違いを示す
- 色でグループを分ける
- 左右に並べて比較できる形にする
といった工夫を加えることで、一瞬で内容が伝わる図解に仕上がります。
このように、「整理」→「構造化」→「伝える工夫」というステップを踏むと、ぐっとわかりやすくなるのです。
4. 図解を作るときのチェックリスト
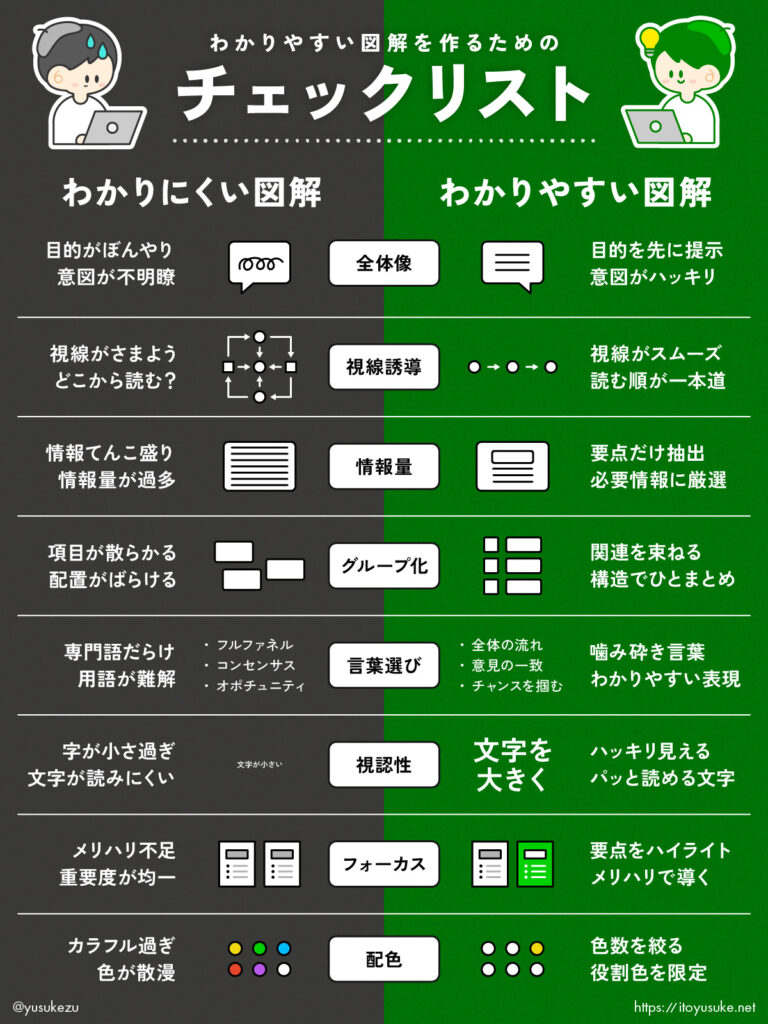
最後に、図解制作の際に確認したい「チェックポイント」をまとめます。
| チェック項目 | NG状態 | OK状態 |
|---|---|---|
| 意図が明確か | 目的がぼんやり | 最初に目的を提示 |
| 視線が通るか | 読み順が不明 | 誘導線がある |
| 情報量は適切か | 詰め込みすぎ | 要点を絞って厳選 |
| 配置は整っているか | バラバラ | 関連ごとにまとめる |
| 言葉は伝わるか | 専門用語だらけ | わかりやすい表現 |
| 読みやすいか | 小さすぎる文字 | パッと読める文字サイズ |
| 情報の強弱はあるか | メリハリ不足 | 重要箇所をハイライト |
| 色の使い方は? | カラフルすぎる | 色数を絞って明確に |
このチェックリストを使うだけでも、図解のクオリティが格段に上がります◎
まとめ|図解を作る3ステップ
- 伝えたい情報を整理する
- 情報の関係性を構造化する
- 見た目を整え、伝える工夫を加える
この3ステップを意識するだけで、「伝わる図解」の精度は大きく変わります。まずは身近なテーマで、1枚の図解を作ってみてください。